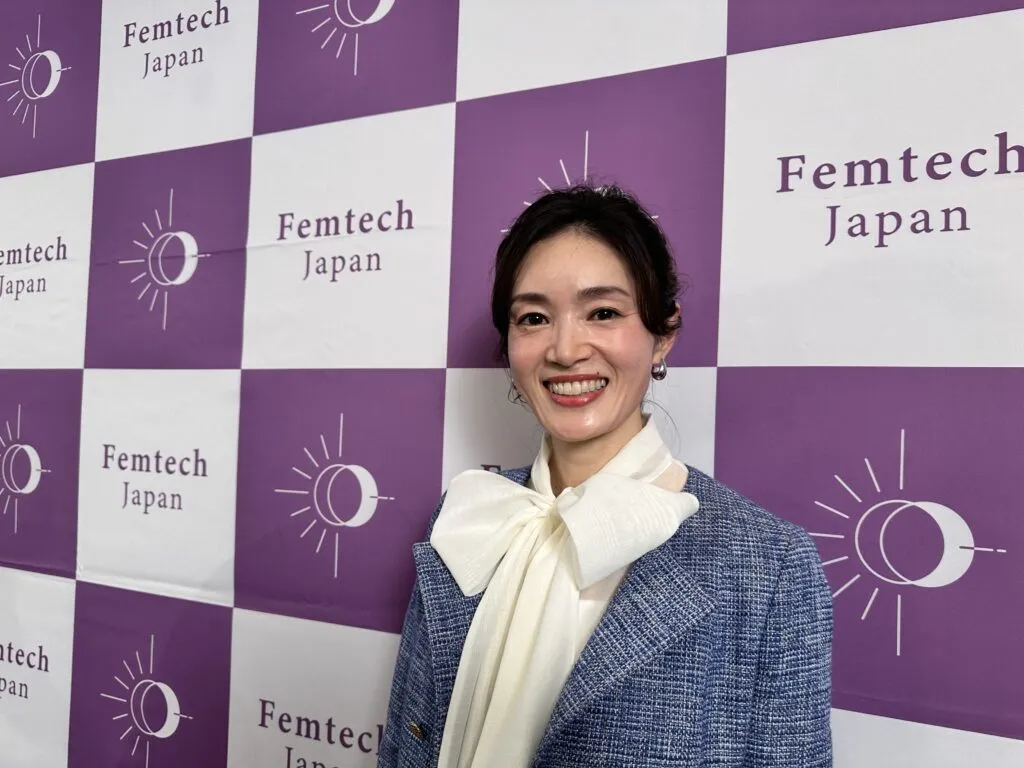Aerial overview of Basel cityscape in Switzerland
スイスの街で、人生初・謎の花粉症に苦しむ母
……そんなわけで(どんなわけだ)、今回は子供の話が一つも出てこないので『ママの詫び状』ではなく、番外編扱いである。
天高く、馬も母も肥ゆる秋。みなさんお元気にお過ごしでいらっしゃるだろうか。実りの秋、文化芸術の秋、美食の秋、しかし秋が来れば思い出す。秋といえば花粉症ですよみなさん(ちーん、と鼻をかむ)。ええ、ご想像通り春だって花粉症だけども!(すみません、ついやさぐれた気分になってしまって。)
ああもう、春も秋も鼻はたれるわ、耳の穴はかゆいわ、頭は重いわ思考力ゼロだわ、しかも薬飲んだらぼーっとするわで、締め切りなんか守れるわけが……って、LEE編集さんホントごめんなさい。
ティッシュが手元にないときは鼻がたれぬようあくまでさりげなく、雲ひとつない秋空を仰ぐふりで虚空を見つめ、「ああしかし、東京の空にはあの謎のフワフワが飛んでなくて本当によかった」と胸をなでおろす私。以前、スイス北西部ライン河畔にある製薬と国際機関の街、バーゼルというスイス第3の都市に家族で住んでいた時、秋になるとその空には見たこともないフワフワした白い植物性の——巨大なタンポポの綿毛のような——何かが舞い、それはそれはしつこいアレルギー反応を私にもたらしてくれたものだった。
いや、大自然に囲まれたスイスにあっては、もはやアレルギー源が確実にそれだったかはさだかでないくらいに各種花粉やあれこれが空中に充満していたに違いないのだけれど、外を歩いてその謎のフワフワが舞うその季節の空気を吸おうものなら、鼻たれっぱなし。というわけで、私にとってその謎のフワフワはつらいアレルギーの季節を知らせる代表者、「自然界からの招かれざる刺客」だったのだ。
ドイツ語圏スイスの鼻かみ事情
でね、そのバーゼルという都市はスイス・ドイツ語という、ドイツ語における関西弁のような位置付けの言語が優先的に用いられている地域で、社会的なマナーもドイツに準じるところがあるのだけれど、ドイツでは鼻をすするのが失礼とされているって皆さんご存知だろうか。鼻をすするくらいなら、どんな人前でも、どんな大音量をたててもいいから鼻をかむ。そのほうがはるかにマナーに適っているのだと。あと、くしゃみをするときは必ず「肘の内側」で口元を覆う。公共交通機関の車内貼り広告にもそうすべしと書かれている次第。
でも当然、質実剛健をモットーとするドイツ文化圏では、日本のようなナントカセレブ的、超高級・皮膚甘やかしティッシュなど売っているわけもなく、ゴワゴワの分厚いティッシュ(日本のキッチンペーパー並み)で鼻かみっぱなしの私は、鼻の下が真っ赤っかになるのが春秋の常だった。子供のインターナショナルスクールに鼻をかみながらお迎えに行くと、カナダ人の母友が「どうしたのよ」と聞くので「謎の花粉にやられてるんよ」と答えると、「ハイテク都市トーキョーから来た人には、確かにこのスイスの大自然は謎が多いかもしれないわねぇ」と笑われてしまった。
つくづく自然界の「恋の季節(=発情期)」はハタ迷惑である

大自然に恵まれたスイスでは、市街地のすぐそばまで森や山が迫り、住宅地のそこかしこにもなんか詩的な、「合歓の木の下で逢いましょう」的な、素敵な花だか実だかをつける木(興味がないのでもはや調べもしない)がいっぱい群生している。それが秋に一斉に繁殖期に入るらしくて、花粉だとかフワフワした長毛の綿毛みたいなのを大気中にボフっと放出するわけだ。
そのフワフワが風に舞い、街を覆うさまはもはや何らかの生物の来襲じみていて、花粉症持ちの私にとってはSFチックな恐怖の光景。だけど子供のインターナショナルスクールのエクスパット(当時の私たち家庭を含むいわゆる『海外赴任者』、仕事で国を離れて住んでいる各国人たち)やスイス人ローカルたちは案外平気らしくて、ケロッとしている。むしろ春先のタンポポの方が困るとか、芝生もキツイわとか言うので、アレルギーって本当に個体差があるものだ。
花粉とは、要は草木のオスが繁殖を目的に同種の草木のメスに向かって放出するものである。その草木のオスの皆さんのご期待には「お応えできない」人間のメスとしては、なぜ応えられない花粉を浴びて鼻の下を真っ赤っかにせにゃならんのかと、常々思っている。草木本人たちは言うならば「恋の季節」で胸踊る季節かもしれないが、哺乳類のホモ・サピエンスにとっちゃいわば植物の一斉発情でハタ迷惑……。季節情緒よりも実害のほうが大きいんですけど(と、また鼻をかむ)。
医療先進国スイスが誇る調剤薬局へ駆け込む
だが、ふふふ、そこは医療先進国のスイスである。中でも当の地、バーゼルは清く豊かに流るライン河を水源に、世界中の製薬系多国籍コングロマリットが欧州本部や工場を置く、一大製薬都市。街なかのあちこちにアポテーケ(Apotheke・調剤薬局)があり、いかにも信頼できそうな真面目そうな表情のスイス人薬剤師の皆さんが、いかにも効きそうだが私には読めないドイツ語パッケージの薬を、カウンターの後ろにたくさん従えておられる。製薬の国スイスなら、きっと私の花粉症を助けてくれるに違いないとにらんだ私は、鼻をかみ続ける手を止め、近所のアポテーケに駆け込んだ。
すると、いかつい印象のスイス人おばちゃん薬剤師(ドイツ系スイス人女性は背が高いうえに、真面目なので余計な愛嬌をふりまかない)が、眼鏡越しに東洋人ねえちゃん(実年齢は十分に中年だが、東洋人は若く見られがちだから致し方ない)の私を見下ろし、「どうしました」ときく。英語で「これこれの事情で謎の花粉症に遭い、大変に困っているのだが、何かよい薬はないだろうか」と訴えると、
「医者にはかかった?」
「いや、まだ」
「わかった。任せなさい」
と彼女は薬棚のほうを向いて、2つの箱を取り出してきた。
まさかのハーブティー!?
 忘れていた。スイスは医療先進国であると同時に、大自然と健康を是とするナチュラル大国でもあったのだ。調剤薬局には、いかにも即効性ありという感じのハイテク薬もあれば、色とりどりのハーブティーや自然派化粧品も取り揃えられていた。薬剤師が出してきたのは、カモミールを中心にいくつかのハーブをブレンドしたハーブティーと、ハーブ抽出水の鼻スプレー。「飲む前に蒸気をかぎなさい。鼻が通るから」「鼻が詰まったらこの鼻スプレーで洗って鼻をかむといいわよ」。
忘れていた。スイスは医療先進国であると同時に、大自然と健康を是とするナチュラル大国でもあったのだ。調剤薬局には、いかにも即効性ありという感じのハイテク薬もあれば、色とりどりのハーブティーや自然派化粧品も取り揃えられていた。薬剤師が出してきたのは、カモミールを中心にいくつかのハーブをブレンドしたハーブティーと、ハーブ抽出水の鼻スプレー。「飲む前に蒸気をかぎなさい。鼻が通るから」「鼻が詰まったらこの鼻スプレーで洗って鼻をかむといいわよ」。
えっ、それだけ? 医療先進国と名高いスイスなのだから、さぞかし飲んだ瞬間に人生がバラ色に変わって痩せて若返ってモテてお金が貯まる錠剤でも出て来るのだろうと思っていたら、ハーブ? 草木に悩まされているというのに、また草なのか……!
「そんなんで治るなら世話ないわ〜」という私のがっかりが顔に出たのだろう、「まずは一週間試してみて。それでも治らないなら医者にかかりなさい」と薬剤師は諭すように言う。
私は8割がたあきらめながら、一週間試してみた。すると症状は、まあ、改善した。半分は気の持ちようでやり過ごした感じがしなくもないが、よくよく考えれば確かに鼻粘膜の保湿と洗浄は花粉を鼻腔から除去するわけだから、そりゃあ効く。で、そのとき思ったのだ。スイスにおける医療とはあくまで健康の維持と増進が目的なのであって、対症療法としてのイルネス(病的症状)治療というよりも、本人のウェルネス(健康な状態)を維持促進するために効くなら、どういうアプローチもアリなのだ。「病は気から」じゃないけれど、ものすごくフィジカルとメンタルが近い気がした。
からだとこころは、繋がっている。
 ドイツやスイスにおいて、健康であるためのそのアプローチは、クラシックからハイテクまで柔軟だ。
ドイツやスイスにおいて、健康であるためのそのアプローチは、クラシックからハイテクまで柔軟だ。
たとえば件(くだん)のホメオパシー。欧州、特にホメオパシー発祥の地、ドイツではホメオパシー薬局が街中に普通に存在し、各種の効能に合わせた白いつぶつぶの各種製剤が、専門の教育を受けたホメオパスによってたくさん売られている。ざっくり言えば、「特定の症状に対して原因となる物質を高度希釈し、砂糖粒に浸み込ませたもの」。東洋人の私から見ると、「ああ、錬金術で科学を発展させたヨーロッパらしいなぁ」と思う。なんだか、すごく魔法っぽい。
それで本当に治るの? 本当は効果はないけれど、口にしたことで精神的に安心や信頼効果が生まれて自己治癒力が引き出される「プラセボ(偽薬)効果」じゃないの、という見解も存在していて、日本の厚生労働省では公式の見解として「特定の症状の効果的な治療法として、ホメオパシーを支持する証拠はほとんどない」と明言している。渡欧前からホメオパシーの存在とその背後の効能議論を見聞きしていた私としては、たぶんホメオパシーという分野はドイツ人が「病は気から」を科学的にというよりも(ドイツ人らしく)やや哲学的に、本気で体系化した学問なのだろうだと考えていた。
私の見立てでは、ホメオパシーは心理セラピーに近い。だからバーゼルへ移住してすぐの頃、あまりに日本と違う文化でわりとがっくりとカルチャーショックに陥った私は、そこであえてホメオパシー薬局へ行って、「新しい文化との摩擦で、精神的につらい私に効くホメオパシーをください」と買い求め、つらくなると口にする、お守りのようにして持っていた。それは効いたかどうか、でもお守りってそういうものだ。
一方で、スイスの医師は抗生物質を絶対に乱発しない。必要な時にこそ最大限効かせるために「念のため」で抗生物質を出したりしない医療には、むしろ症状を細かに知るための丁寧な診療が必要となる。スイス生活で1年半ほど抗生物質抜きだった私が、その後重めの細菌感染にかかって抗生物質を処方されたとき、驚くほどすっきり効いた。
からだとこころは、繋がっている。
以来、のちの私は全面的とは言わないにしても、じんわりとハーブに頼る人生だ。風邪を引いたらジンジャーやカモミール、胃腸の調子がすぐれなければミント、それぞれハーブティーを飲んで寝る。香りもボディケアもどちらかというとハーブを信じる。「そりゃ、西洋のハーブは東洋の漢方と同じだもんねぇ」と思う。人は草木と共生して生きるのだ、花粉大迷惑!とばかりも言っていられないなぁ、うむ。

河崎環 Tamaki Kawasaki
コラムニスト
1973年、京都生まれ神奈川育ち。22歳女子と13歳男子の母。欧州2カ国(スイス、英国)での暮らしを経て帰国後、子育て、政治経済、時事、カルチャーなど多岐に渡る分野での記事・コラム執筆を続ける。2019秋学期は立教大学社会学部にてライティング講座を担当。著書に『女子の生き様は顔に出る』(プレジデント社)。