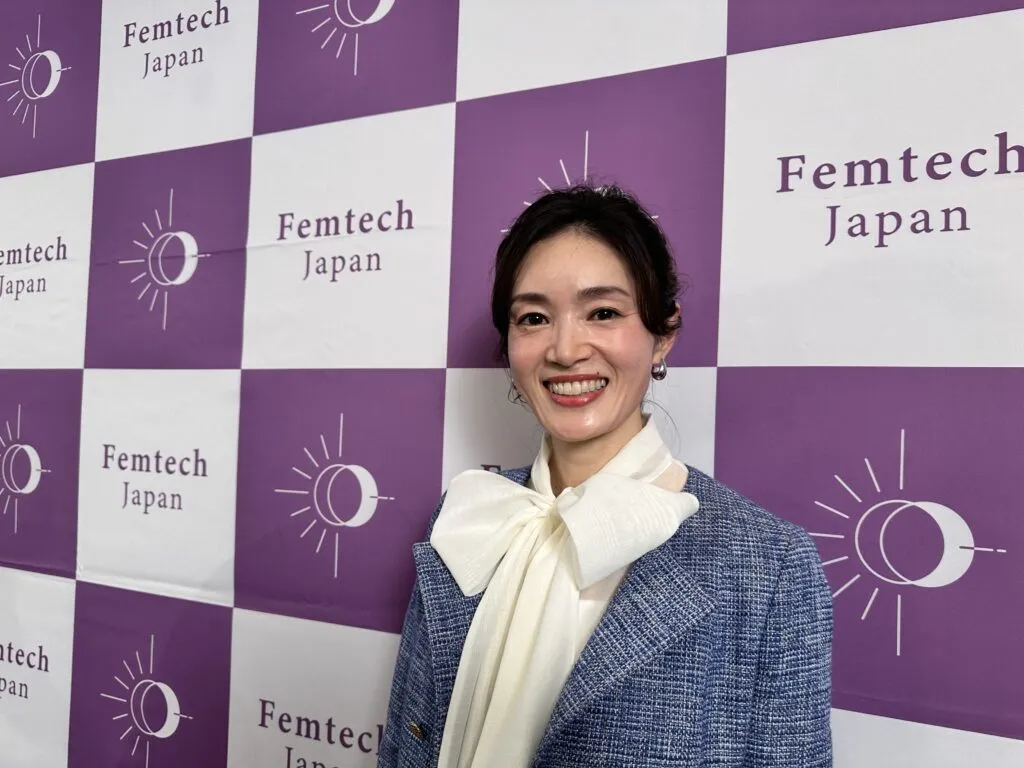時代との距離感を推し量りかねていた数年間
「あらかじめ決められた恋人たちへ」(略して、あら恋)はキャリア22年のインストルメンタルバンドだ。リーダーの池永正二さんが生み出す、独特のエモーショナルな音楽から、“叙情派インストルメンタル・ダブ・バンド”と紹介されることも多い。最近は映画『宮本から君へ』への作品提供をはじめ、劇伴作家としても知られる池永さんだが、3年半ぶりに“あら恋”の新作が届いた。それが震えるほど、素晴らしかった。ヘッドフォンから流れてくる音に吸い込まれ、いつの間にか涙がこぼれていた。全7曲60分と長い作品だが、長さを感じない。かといって、あっという間でもない。濃密な時間を堪能した、といったらいいか。これまでの作品ももちろん素敵だが、これはとりわけ傑作なのでは……!?と感動した。ここ数年「スランプだった」と語る池永さん。悩みを乗り越えて作り上げた『……』(リーダー、と読みます)は新境地を拓いたといっていい。円熟したスキルと40歳を越えてなお、ナイーブでフレッシュな感性を持ち続ける池永さんならではの世界観だ。これはぜひともお話を伺いたいと思い、お会いしてきました。DUB PAとしてバンドを支える石本聡さんも撮影後、加わってくださり、和やかにお茶を飲みながらのインタビューになりました。

あらかじめ決められた恋人たちへ●池永正二をリーダーとするシネマティック・インストDUBユニット。1997年、池永のソロユニットとして大阪で活動を開始。2008年に上京し、以降はバンド編成で活動している。現在は池永正二(鍵盤ハーモニカ、エレクトロニクス)、劔樹人(ベース)、クリテツ(テルミン、パーカッションetc)、オータケコーハン(ギター)、GOTO(ドラム)、ベントラーカオル(キーボード)、石本聡(DUB PA)の7名に、PAを加えた8人がコアメンバー。鍵盤ハーモニカやテルミンといった楽器が奏でるノスタルジックでメロウな音色と轟音ギターやダイナミックなキーボード、変則的かつ現代的なビートが絡み合う音楽は唯一無二の世界観を持つ。池永は映画『宮本から君へ』や『ブルーアワーにぶっ飛ばす』など、劇伴作家としても活躍。他のメンバーも多彩な個人活動をしており、スキルの高いプロ集団として、ミュージシャンの間でもリスペクトされている。
――本当に! マジで! 新作の『……』(リーダー)、素晴らしかったです。最初に先行シングルの『count』を「お、あら恋、新曲出たのか」となにげなく仕事中に聴き始めたら、キーボードを打つ手がピタリと止まりました。耳が釘付けになってしまって。なんて美しい曲でしょうか……。
池永:いやあ、そうした感想いただけると、うれしいですね。
――それで、「これはアルバム全体すごいことになっていそう!」と音源サンプルをいただいたら、とてもドラマチックで、エモーショナルで、期待以上にすごいことになっていたので、慌てて10月の新宿区のフェス『-shin-音祭』に足を運び、久しぶりにライブも拝見しました。高い熱量と浮遊感が会場全体を包み込む、これまたすさまじいライブで感動しました。
池永:あ、いらしていただいていたんですね。ありがとうございます。
――あら恋はインストルメンタルで歌詞はないのに、アルバムからもライブからもメッセージが雄弁に伝わってきた気もしました。前回のアルバム『AfterDance』は曽我部恵一さんなどのゲストボーカルや詩人の和合亮一さんの朗読といった「言葉」にフォーカスした作品でしたが、今回の『……』はあら恋の原点に返った、完全なるインストルメンタルでありながら、まさに新境地を拓いた印象を受けています。この3年半の間に何があったんですか?
池永:僕はいつでも迷っている人間ですが(笑)、ここ数年はとりわけ迷っていました。前作は新メンバーでバンドっぽい音をやりたくて、次に20周年で再録音のベスト盤を出して一旦「。」が付くと曲ができなくなった。まさかのスランプ。作るんですが以前と一緒だったり今にマッチしない。音楽的にも社会情勢的にも、“時代との距離感”を推し量りかねるといったらいいのかな……。なんか今、世の中がちょっと嫌な感じがしませんか? みんなが必要以上に「キーッ」となっている気がするんです。僕、SNSがあまり得意ではないんですが、自分の思った事や感じたことを短い言葉でネットにアップして、それがフォロワー数やビュー数とか人気度が数値付きで公開されて、日々視聴率競争みたいな。そんなツールが日常に入り込んでるからなんだかしんどいなあ、と思うんです。すごく窮屈な空気が蔓延するこの時代との距離感をどうとったらいいんだろう、惑わされずにいられるんだろう、そうしたなかで自分はどんな音楽をやりたいんだろう、と迷ってしまった。
石本:そうだね。池永くんはここ数年、悩んで、もがいているように見えました。あら恋のメインコンポーザーは池永くんだから、池永くんのペースで作ればいいと思ってたけど、今年になって、「曲が出来た!」と連絡きたときは、やっぱり、うれしかった。それも、本当にすごくいい曲で。池永くんとのつきあいは長いですが、キャリアを重ね、40歳を越えて、こんなに新しいものを生み出せるって素晴らしいなあ、と僕も感動したくらいです。
池永:とはいえ、バンドのメンバーには「ここはこうしたほうがいい」とダメ出しされたところもありましたけどね(笑)。
――あら、そうなんですね。池永さんが絶対君主かと思っていました(笑)。
石本:池永くんも丸くなって(笑)。
池永:1997年に僕ひとりで「あらかじめ決められた恋人たちへ」という名義で活動し始め、いろんなメンバーとやってきました。2015年に今のメンバーになってから、個々の個性が表現できるような楽曲作りになりました。当て書きのような感じです。個性の強い面白いメンバーばかりなので。だから“バンド感”は今が一番強い。それから、『宮本から君へ』もそうですが、映画などの劇伴を手掛けるようになったのも影響していると思います。映画は本当にたくさんのスタッフが関わるチーム仕事だから、人の意見に自然と耳を貸せるようになったのかもしれません。
大切にしたいのは、感情が揺れ動いている過程やレイヤー

――あら恋のバンド感や編成って独特で捉えづらいんですが、たとえば、今の“KIRINJIの堀込高樹さん方式”と近いですか?
池永:そうそう、たぶん、それに近いです(笑)。
――腑に落ちました(笑)。それで、すごく迷っていたのに、何がきっかけで迷いが晴れたんですか?
池永:これ、というハッキリしたきっかけはないんです。でも、たとえば小学4年生の娘とキャンプに行ったりすると、楽しそうに遊ぶ彼女の顔を見ているうちに、モヤモヤした気持ちが晴れる。さっき話した今の社会に感じる窮屈感がなくなるわけじゃないけど、今この瞬間の楽しさは確かなもの。当たり前ですが、人生も社会も良いこと嫌なこと、いろんなことがある。僕にとっては正解でも相手にとっては大間違いだったり、白黒つけられないとても曖昧なものですよね。感情も揺れ動きます。それでふと、物事や感情を一言で言いきることへの強い拒否感が、スランプの原因だと思った。僕が大切にしたいのは過程やレイヤーなんです。両極端のどちらかをパッと選びたいわけじゃなくて、その間で揺れ動きながら、結論を出したい。その過程こそが、どこかで結論を出すにしても大切だと思うし、自然な気がします。だから、その曖昧さ、過程やレイヤーの尊さをテーマにしようと思った。そこから、ワッと曲がどんどん生まれました。
石本:本当に7月に「アルバム作ります!」って連絡が来た。池永くんの中で、ようやく何かが見えたんだなと、ヒシヒシと感じましたね。あろうことか、9月には出したいとか言い出して(笑)。それはちょっと現実的に難しいから、11月リリースになりました。
――それでも出来立てホヤホヤ取って出し、ですよね。自主レーベルならではのスピード感。最近、サブスクリプションの広がりもあって、自主レーベルも含めてインディペンデントとメジャーの境界がそれほどなくなった気がしていますが、あら恋は自主レーベルをスタートして以来、何か苦労はありますか?
池永:もっと良い曲を書けよ!って曲を書くのは自分だし、もっと売り込めよ!ってそれも自分だし、自分でレーベルをやっていると何かのせいにできないのはとても健康的です。人にも恵まれてますし、大変ですが楽しくやっています。メンバーにもスタッフにも本当に感謝です。ただ、僕は事務的なメールでも書くのに悩んじゃうから、単純にそういうことに時間をとられるのが大変(笑)。
――メールを書くのに時間がかかる……。となると、Twitterも書くのに時間がかかりそうですね。お知らせ以外、あまり更新がない理由がわかりました(笑)。
池永:Twitter、時間がすっごいかかります。でも、もう少し、更新しないといけませんよね……。
――いえいえ、それならTwitterなんてお知らせさえあればいいので、作品作りに時間と労力を使ってください(笑)。
石本:ふいにアップされる池永くんのツイート、すごく味わいがあっていいんですけどねぇ。
――それでは、ふいに思いついたときのツイートを楽しみにしていますね。ところで、もう一度、本題の新作『……』の話に戻りますが、アルバムタイトルは「リーダー」と読ませるんですよね? そのまんまといえばそのまんまですが、トリッキーなタイトルともいえます。
池永:さっき話したように、白黒ハッキリつけられない過程やレイヤーって、うまく言語化できないでしょう?
――言葉にしろ、って言われたら、言いよどみますね。
池永:「うーん……」って「……」と沈黙する間のさまざまな感情を曲にしたつもりなので、沈黙を表す『……』としました。完全なインストルメンタル作品にした理由も同じですね。
――なるほど。『……』というタイトルの理由は曖昧ではなく明快ですね(笑)。それから、全7曲60分とイマドキのアルバムとしては長い作品で、起承転結を意識した「流・ケ・路・未」という4部構成にされています。ちなみに、この4つはどう読むんですか?
池永:りゅう、ケ、みち……最後は……み? すみません、読み方を考えていませんでした(笑)。
――考えてなかった! こちらこそ、すみません。曖昧さを無理に明確にさせようとしてしまいました……。何が言いたかったかというと、インストルメンタルの魅力のひとつは歌詞がないぶん、曲が狭い意味に限定されることなく、聴く者に大きく委ねられる点だと思っています。本作もまた、聴く人ひとりひとりの物語や感情に寄り添うと思いますが、一方で、たとえば『ヒズミ』『降っている』『外』といったタイトルがつけられている意味も曲ごとにわかる気がしたんです。共鳴できるというか。
池永:最近、アルバムは通して聴かれる機会が少なくなっていますが、小説や映画は短編よりも長編に作家性を強く求められる傾向があります。自分の音楽に迷ったからこそ、改めて原点に戻り、60分という長尺でしっかり物語性と作家性がある作品を作りたいと思ったんです。作品に込めた思いやメッセージが雰囲気としてでも伝わって共鳴できたら、ものすごくうれしいですね。
――壮大なスケールのクラシックアルバムを聴いた時と似た感触がありました。轟音ギターが鳴り響き、あたたかみのある鍵盤ハーモニカやテルミンの音があり。かと思えば、今の音としか言いようがないビートが刻まれ……と、複雑な組み合わせの妙が圧巻でした。長く聴き継がれる普遍性はありますが、ものすごく「今という時代」が切り取られた空気感も同時に感じます。本来、インタビュアーとして音楽的に深堀りをするべきだと思いますが、テクニカルな要素については、あえて考えずに音の洪水に身を任せて楽しみたい、という気持ちになりました。気軽に聴いたら、いつの間にか、素晴らしい景色の場所に連れていかれていたので、この記事を読んで聴いてみよう!と思ってくださった読者さんにも「とにかく聴いてみて!」と言いたいです。
池水:いやいや、それでいいんです、気軽に聴いてください(笑)。「とにかく聴いてみて!」と思ってもらえてうれしいですよ。
絶望せずに、生きていく

――ところで、「あらかじめ決められた恋人たちへ」というバンド名は、日本映画『あらかじめ失われた恋人たちよ』からインスピレーションを得てつけられたそうですね。今でこそ、日本語の文章になったバンド名は珍しくありませんが、22年前は珍しかったと思います。なぜ、こうしたバンド名にしたんですか? 当時、他にありましたっけ?
石本:「暗黒大陸じゃがたら」とか? 後に「JAGATARA」になったけれど。
池永:少なかったですね。でも、海外なら「Red Hot Chili Peppers」みたいなバンド名が珍しくないじゃないですか。日本語に訳したら、「赤くて熱い唐辛子たち」ですよ(笑)。だったら、日本語の長いバンド名があってもいいじゃないか、と思って。
――22年経ち、あらかじめ決められた恋人たちへ、という詩的なバンド名に込める思いは変わりましたか。
池永:どうだろう? もちろん、20代前半の自分と40代の今の自分は同じではないけれど、喜怒哀楽の真ん中を大切にしたいという根本的な思いは変わらないですね。いや、真ん中も違うかな……。人生には喜びの中に哀しみがあったり、怒って楽になったり、そんなヒマもなく慌ただしく過ぎていく時もあれば、なんにもうまくいかなく無駄に思えた日々が素晴らしい瞬間に昇華される時もあるわけで。嫌なことがあっても、そればっかりじゃないし、結末も絶対わからないんだから、悩みながらも絶望せずに生きていく、という気持ちに変わりはない、ってことでしょうか。
――絶望せずに「未」の日々を生きていく。Life goes onですね。嫌なニュースが多い昨今ですが、あら恋の曲を聴いて前を向くことにします。今日はお忙しいなか、ありがとうございました。
池永:どうもありがとうございました~!
取材・文=中沢明子 撮影=齊藤晴香

(撮影/タイコウクニヨシ)
『……』リリース記念ワンマンライブスケジュール
2020年1月10日(金)
新代田FEVER
2020年2月15日(土)
大阪 北堀江 club vijon
2019年11月24日(日)
詳しくは公式サイトでご確認ください。

あらかじめ決められた恋人たちへ
『……』
-流- 1.count 2.ヒズミ
-ケ- 3.降っている 4.ハレ
-路- 5.外 6.neon 7.線
-未- 8.日
*CDのほか、ApplemusicやSpotifyなどのサブスクリプションでも配信。

中沢明子 Akiko Nakazawa
ライター・出版ディレクター
1969年、東京都生まれ。女性誌からビジネス誌まで幅広い媒体で執筆。LEE本誌では主にインタビュー記事を担当。著書に『埼玉化する日本』(イースト・プレス)『遠足型消費の時代』(朝日新聞出版)など。