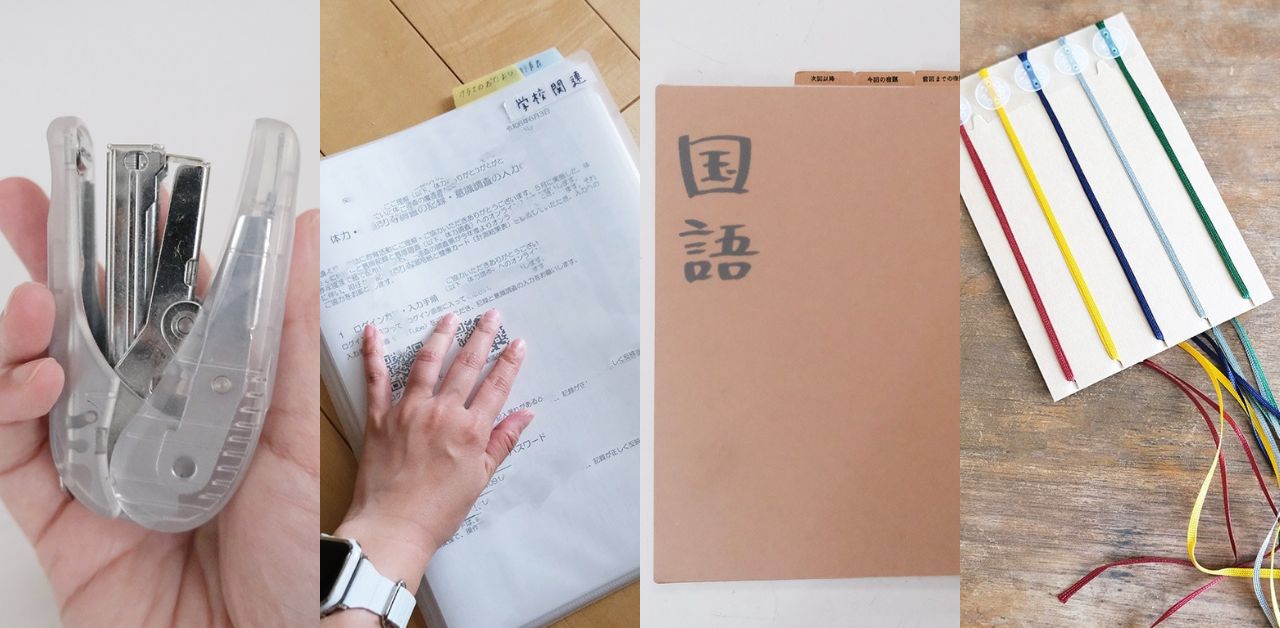『新聞記者』の藤井道人監督が最新作を語る ――『宇宙でいちばんあかるい屋根』に込めた思い
-

折田千鶴子
2020.09.02
映画『新聞記者』の大ヒットにより、一躍、次回作が待ち焦がれられる存在となった藤井道人監督。実は私、まさか『新聞記者』があんなに大ヒットになるとは思っていませんでした。というのも、作品は衝撃的ですし、もちろんとっても面白いのですが、“映画はフィクション”とうたいつつも、現政権に真っ向から挑む硬派な社会派映画を、日本人の観客がこぞって観に行くとは思わなかったのです。だからこそ、そんな作品を大ヒットに導いた手腕が高く評価されましたし、大ヒットしたことに、“日本も捨てたもんじゃないな”という希望を抱けたように思えました。多くの人の「よくぞ作ってくれた」という喝采とエールが聞こえそうな気がしたというか。

藤井道人
1986年8月14日生まれ。日本大学芸術学部映画学科卒業。2010年に映像集団「BABEL LABEL」を設立。『オー!ファーザー』(14)で長編監督デビュー。その他の作品に、『青の帰り道』(18)、『デイアンドナイト』(19)『新聞記者』など。『新聞記者』は日本アカデミー賞で作品賞、男優賞、女優賞で最優秀賞を受賞。監督賞、脚本賞、編集賞で優秀賞を受賞。『ヤクザと家族 The Family』が21年公開予定。
とはいえ実はそれ以前から、次世代を担う若手監督として高く評価されてきた藤井監督。
山田孝之さんがプロデュースを務めたことでも話題となった『デイアンドナイト』もズッシリ下っ腹に響く力作でした。さらにその前の、今をときめく横浜流星さんが大ブレイク前夜に出演された『青の帰り道』も素晴らしくて。ラスト、色んなことを胸に秘めて大人になっていくんだな、という切なさで胸が締め付けられる、後ろ髪引かれ系の青春映画でした。
男性キャラクターからヒロインを映し出す
そんな藤井監督の最新作は、野中ともそさんの同名小説を映画化した『宇宙でいちばんあかるい屋根』。
思春期真っただ中の14歳の少女つばめが、ある日ふらりと現れた老婆・星ばあとの出会いを通して、自分の居場所を確信し、大切なもの、大切な人に気付いていく物語――。

『宇宙でいちばんあかるい屋根』
© 2020『宇宙でいちばんあかるい屋根』製作委員会
2020年/日本/1時間55分/配給:KADOKAWA
監督・脚本:藤井道人
出演:清原果耶、桃井かおり、伊藤健太郎、吉岡秀隆、坂井真紀、水野美紀、山中 崇、醍醐虎汰朗
9月4日(金)より全国ロードショー
――今度もまたガラリと方向性の違う作品を選ばれましたね。悩みを抱えた思春期ド真ん中の女の子の心情を捉えるというのは、なかなか大変なことではありませんでしたか。
「どの作品も脚本を書いているときに難しさは感じますが、僕が常に難しい題材を選んでいるとも言えます。だからおっしゃる通り、“つばめの台詞、全然わかんねぇぞ”という感じでした(笑)。そうするうちに、すべての男性キャラクター、――元カレのマコト(醍醐虎汰朗)、お隣の亨くん(伊藤健太郎)、つばめのお父さん(吉岡秀隆)、お習字の牛山先生(山中崇)などに自分を寄せていったんです。マコトには中学時代のクサクサしていた頃の僕、牛山先生には若い子に何かを教えてあげる僕、亨には隣の女の子に優しくする僕、そしてお父さんには父になった目線の僕、と。「つばめ」から何かを描くのではなく、男性キャラクターの複合的な目線で「つばめ」という女の子を描いたら、すごく描きやすくなりました。現場では、僕はさながら“星ばあ”として清川果耶ちゃんの横に居ようとしました」
――映画における“ファンタジー加減”が絶妙で、すんなり心に寄り添うようにすっと入ってきて、とても心地よかったです。その辺りの描写の塩梅や加減で苦心したことはありましたか。
「果たして星ばあはいるのかいないのかも含め、映画は原作より少しだけファンタジー要素を弱めました。「宇宙」についても、リアリズムというよりナチュラルに存在していて欲しいと思ったので、最初に抜いた方がいい定義は「ファンタジー」だ、と。夢のシーンも、他のシーンから地続きであるところだけを選んで。要は、14歳のときは“そう見えた気がした”というのがギリギリのライン。夏の夜は真っ暗だけど、あんな風に青白い夜に見えたことがあったな、と記憶にある気がするもの。ファンタジーまではいかない、脳内に写実として残っているものを絵画のように撮ろう、と決めていました。頁をめくっていく感覚になる映画になればいいな、と」
大人をちゃんと肯定してあげる映画にしたかった
――星ばあと出会い、色んな話をする屋上でのシーンの数々が印象的です。あの屋上のビル探しなど、ロケハンには相当こだわったのでしょうか?
「実は、あの場面はセットで、星空などもすべてCGで作っているんですよ。……そんなに驚いてもらえると、CGを手掛けたスタッフがノイローゼ寸前まで頑張ったので嬉しいです(笑)。このトーンで描いてきて、屋上に行ったら、あ、セットだ、と見えちゃうなんてあり得ませんから。とにかく果耶ちゃんと星ばあ役の桃井かおりさんが、一番お芝居をちゃんとできる環境を選びました。夏の大空、雲ひとつ、星ひとつにも、すべて意味をこめ、細かいこだわりをもってCGを作っていったので、発見して欲しいです。つばめが少し悩んでいるときは雲も多く、少し青いとか。星の瞬きが少ないときは、命がどんどん少なくなってきているとか。月の満ち欠けにも意味があるので、その辺りも楽しんで欲しいです」

つばめは習字教室のビルの屋上で、不思議な星ばあと出会います。なんとなく言葉を交わすようになったツバメは、いつの間にか悩みや心の中に溜まっていたことを話し始めるのです。何度も登場する、この屋上のシーンが、ちょっと幻想的で、とっても印象的!
――つばめ役の清原果耶さんは、『デイアンドナイト』に続く起用です。この年にして既に熟練級の自然な演技と味わいを出されますね。監督の演出は、動きを含めかなり細かいと聞いたことがあるのですが……。
「果耶ちゃんは、既に一緒にやっているのもあり、素晴らしいので僕が細かい演出をつけることもありませんでした。僕が細かい演出をつけるときは、自分の映像の世界に馴染んでいない人、僕の世界でリアルじゃないと思ったな時だけなので。果耶ちゃんは向いている方向も一緒だし、“つばめとして生きてください”、“了解です”というだけでした。ただ、すんなりセリフが出ないときは、相手役の方を座らせてからセリフを言ってみよう等々を試すと、フッとセリフが出てくることはありました。僕がしたのは、彼女が詰まったとき、その前の岩を取り除くという作業だけでした」
――大ベテランの桃井かおりさんに対しては、どんな感じだったのでしょう?
「桃井さんは、“監督、このセリフより、こういう感じの方がつばめの気持ちに寄り添えるんだけど、やってもいい?”みたいな感じで、常にセッションに近い感じでやって下さいました。“こんな音出せますか?”、“出せるよ~!”みたいな。まさにスパーリングしている感じで、すごく楽しかったです。果耶ちゃんとは、茶道みたいな感じ(笑)」
――観た人がいろんなことを感じ取れる作品ですが、本作に込めた思いを教えてください。
「今の時代、“誰が俺の人生をこんな風にした!?” と社会のせいにしたくなったり、ネットで誰かを攻撃したり、みんな色々あると思います。でも“いや、大丈夫。あなたの人生、それでいい、それで正しいんだよ”と、30を超えて大人になった人たちを、ちゃんと肯定してあげられる映画にしたいな、と思っていました。そういうことを言ってあげられる人がいないなら、そういうことを言ってくれる映画があってもいいじゃないか、と。 “あの時の自分はつばめだったな”とか“自分の中にもこんなマコト君がいたな”など、なにか感じてもらえたら。観終えた瞬間は“良かったな”程度でもいいから、数年後、あの屋根の画などワンカットでもいいから残ってくれている、そんな映画であったらいいな、と思っています」

――監督自身について、少し聞かせてください。常に次はこう来たか、と驚かされるのですが……。
「本作も、『新聞記者』のときと同様、“自分に向いてなさそう”だと思うことが、“よし、やってみよう”と動機になりました。これを30代前半のうちにやっておいたら、後半でその体験が生きてくるだろう、と。撮ったことのない作品を、多面的に選んでいます。ドMなので(笑)。成功体験がある作品を、なぜもう一度撮らなきゃならないんだ、という気持ちがあるんです。やったことがないからやってみる、ということに意味があると思うタイプで。周りから「ブレブレだな」と言われようが、構わない。ブレているわけじゃなく、振り子なんだ、と。単純に自分が楽しいから、でもありますが」
――自分の中で“得意”を意識することは?
「基本、根暗なので(笑)、裏で何かやっているような『デイアンドナイト』みたいな方が、自分っぽいな、とは思います。ただ作品には、その時の自分の社会的な立ち位置や環境がすごく影響しています。『青の帰り道』や『デイアンドナイト』を作っているときは、映画監督として全く評価はされていない時代だったし、会社も上手くいっていない上、社会も東日本大震災以降ずっと揺れて不安定だったし、そういうものがもろに作品に出ていると思います。20代はずっとキツかったな。でも、そういうものを全部、作品で吐き出したから、逆に『宇宙でいちばんあかるい屋根』みたいな作品の脚本が書けた。『宇宙』で明るいものが満たされたので、次はまた『ヤクザと家族』という非常に暗い作品を撮って。両方やってバランスを保っているところはあります」
――多数舞い込むオファーの中から、“それを俺が撮る意味”を見出して引き受けるのですか?
「いや、「俺が撮る意味」的エゴイスティックな部分は特にないんです。それより常に「なぜこれを今、撮るか」を常に考えます。その映画を公開し、観客や社会とどういう対話をするのか、それが一番大事。そこさえ折り合いがつけば、どんな映画でも大丈夫だと思います」


折田千鶴子 Chizuko Orita
映画ライター/映画評論家
LEE本誌でCULTURE NAVIの映画コーナー、人物インタビューを担当。Webでは「カルチャーナビアネックス」としてディープな映画人へのインタビューや対談、おススメ偏愛映画を発信中。他に雑誌、週刊誌、新聞、映画パンフレット、映画サイトなどで、作品レビューやインタビュー記事も執筆。夫、能天気な双子の息子たち(’08年生まれ)、2匹の黒猫(兄妹)と暮らす。