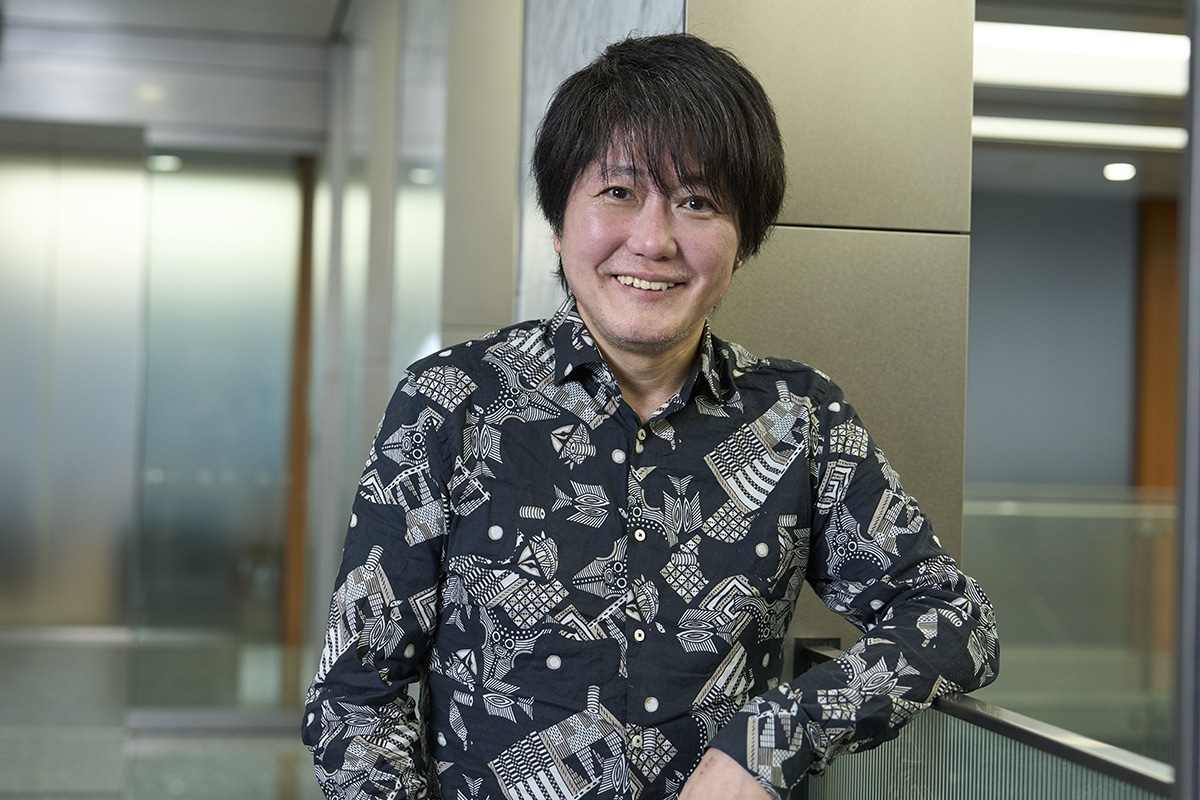無痛分娩や帝王切開は「母として邪道」ですか?

産科医療の現場を描き共感を集めるドラマ『コウノドリ』で、TOLAC(帝王切開後に経膣分娩を試みること)の妊婦が扱われ、大きな反響を呼んだ。帝王切開で産んだ一人目の子を「かわいいと思えない」と悩み、それは帝王切開だったからではないかと考える母親が、第二子は自然分娩で産みたいと命を賭けた自己犠牲をもって願うエピソードに、LEE読者の皆さんが流した涙は相当な量にのぼったんじゃないかな、なんて思っている。
一度帝王切開をした子宮には、当たり前だけれど切開創が残る。すると出産レベルの圧をかけた時に、その傷跡から子宮が破裂する可能性が高いため、それを避けるために一度帝王切開をした女性は次の出産以降も帝王切開となることが多い。でも、「上の子をかわいいと思えないのは、私が帝王切開で産んでしまったからではないか」と、次は「お腹を痛めて、下から」産みたいと望む女性が、少なくないのだという。
ドラマで印象的だったのは、その母親が繰り返す、「今度は下から、お腹を痛めて産みたいの。いいお母さんになりたいの」との言葉。「いいお母さん」という漠然とした、しかも誰もその基準やものさしを示すことなんて不可能な概念に祈りを捧げるかのような姿に、私は「いいお母さん」ってなんのことを指しているんだろうなぁ、と天を仰いだ。
「いいお母さん」に実体なんかない。それは不透明でもやっとした霞のような概念に過ぎない。でも、そのもやっとした偶像を私たちは老いも若きも男も女も崇拝し、「母たるもの、そうあらねば」と信じる。ドラマで、TOLACの妊婦は陣痛に耐えながらも最終的に子宮破裂の危険性が高まり、帝王切開を受け入れるのだけれど、でもそのきっかけは夫と子供が「ママは、(こんなに頑張ったんだから)いい母親だよ」と言った、外部からの「承認」だったのだ。
彼女の中では、いいお母さんであるかどうかが自分の納得感や自信ではなく、他者からの承認で決まった。ドラマはハッピーエンドだったけれど、母親の承認欲求や現代女性の自己肯定感といったところへ、そっと問題提起もしていたように思う。
私たちはロボットでもクローンでもないから、100人いれば100通りの個性ある体を持っているのに、ましてその個性が母体だけでなく赤ちゃんの側にもある出産という、何一つ予想通りにいくとは保証できない場面で、「ちゃんと」って何だろう。
「昔から」の方法で「自然に」産むのが正統な出産で、そうでない人工的な力を借りたような方法は「邪道」、「母親の怠慢」、「母性の欠如」なの?
それは出産法によって母親を差別しているようなもので、浅はかで無神経なだけでなく深刻な問題発言であることに、社会(男性も、出産を経験した女性でさえも)はわりと無自覚なのではないかな。ううん、そんなあからさまな発言などしなくても、心のどこかでそう信じてしまっている、あるいはその考え方に「疑問を持ったことがない」人は、もっといるのではないか、と思う。
禊(みそぎ)、そして「良い母親」ヒエラルキー

このドラマを見終えた、ベテランの母親がこんな本音を教えてくれた。「私も、VBAC(帝王切開後経膣分娩=TOLACが成功した出産)で二人目を産んだんですけれど……。今思えばあのときの私は、1回目の禊のようなものとして、下から産む、が必要だと思っちゃってたんですね」
「禊」とは、母親が一人で背負うにはあまりにも大きく、強い意味を持った言葉だ。「罪や穢れを洗い清める」ことだ! 子供を帝王切開で産んだ、下から産まなかったことが、母親としての「罪」であり、母性を「穢す」ものだったと彼女は自分を責めていた、のかもしれない。あるいはそこまで深刻でなくとも、母親としての後悔があったということだ。
どう産もうが、自分の体を最大限に使って、新しい命を無事にこの世へ送り出したというのに、その「無事に送り出した」だけでも十分以上だというのに。「いい母親」「完璧な母性」の呪縛は、母親に罪の意識を植え付けるのだと、衝撃さえ感じた。
実は、私も第一子を計画無痛分娩で出産した。当時まだ大学に通学中だったから、2ヶ月の夏休みをフルに乳児と過ごそうと、夏休みの初日に出産すると決めた。確かに、若かったゆえの合理主義。ひょっとすると「浅はか」「易きに流れた」と批判されても仕方ないのかもしれない。でも、無事に生まれて、可愛い可愛いと育てていた。ところがあるママ友に言われたのだ。
「無痛分娩? ちゃんとお腹を痛めて産まないと、子供をちゃんと愛せないっていうよね?」
「えっ、しかも計画分娩? 自然に任せないで、子供の誕生日を親が勝手に決めちゃって、星占いとか大丈夫なの?(笑)」
星占いかぁ〜! そりゃ一本取られちゃったな、愉快、愉快……と、もうその娘も21歳までスクスク育ちあがった今なら笑って対応できるけれど、当時は「子供の運命を私が曲げてしまったのか……」とショックだった。まぁでも娘の誕生日以降1ヶ月ほどは同じ星座だから、ダイジョーブダイジョーブ。でも「星占い大丈夫なの?」って……。母親って、ひとたび子供のこととなるとどんなことでも心配するものだし、最終的に自分を責めるものだ。それはたぶん、自分が「この子をこの世に産み出した」という自覚が否応なしについて回るからなのだ。
その後も、ママ友の間や年上の女性、年下の未婚女性との会話などで、自分が当事者ではなくても何かとお産の方法による母性差別を見聞きする場面はあって、他の女性を非難するときにわざと使ったりする人もいた。不思議と、そういう人たちは勝手に「良い母親」ヒエラルキーを作って、あの人は誰々より上、あの人は下、と順番をつけているようだった。女性は、こと「女である」ことに関して、他者に容赦なく牙を剥くことがある。牙を剥くというイメージ通り、そこには理屈ではない、動物的な何かがあるように思う。
女性のいろいろな物語が交差する「妊娠・出産」

産婦人科とはまさにその女性の動物性を扱うところなわけで、だから色々な物語が交差する。妊娠や出産はそれらの物語が生まれる最たるもので、さらに「母性プレッシャー」という目に見えないものが絡まって、患者の側には迷信や神話としか呼びようのない、奇説・怪説が跋扈(ばっこ)する。
私もそれらの「トンデモ」な迷信・神話でイヤな思いもした。そんなアホなと笑ったし、自分の方がそんなのを信じてしまって、アホかと笑われたこともある。だけど、(もちろん全てではないにせよ)医療がその個々の物語や信じているものを「科学的でない」「無知」「くだらない、相手するに値しない」かのように斬って捨てる男性的な理屈––「科学的な根拠によってのみ証明される論理」優位の世界だったことに、私はやはり違和感がある。
結局女体のあれこれの悩みを同じ「女体」当事者として救い上げてくれていたのは、助産師さんや看護師さんという、時代のせいもあって医療のサブに位置付けられた人たちだったのではなかったか。だから前回のコラムで取り上げたような「完全母乳信仰」の文脈で語られる「食べ物によって乳腺が詰まりやすくなる」なんて話などは、現代の知恵のついた人々には「トンデモ」と映るような理屈であるにせよ、すべてがトンデモだとも捨てきれない。
妊娠出産の神話の中には、まだ日本が貧しく栄養が偏っていた時代の名残や、今のように物資が豊富でなく、かつ女性の地位が低くいたわれられない時代に女性が健康な妊娠生活を進めるための先人の知恵などが、理屈ではない文化、経験知の集結のようにして連綿と生きてきたものもあると思う。
エビデンス(科学的根拠)のある正統な医学以外はトンデモだ、無知なんだリテラシーがないんだと切り捨てるのは、「それでもなお、なぜそこに光を見出し、すがってしまう患者がいるのか」と患者の背景に思いが至っていない。視野の狭い強者の論理と映ることもあるかもしれない。
冒頭の話に戻ろう。「自己犠牲がなければ、いいお母さんになれない」と信じてしまう母たちの気持ちの理由は、何だろう。それは、「自己犠牲があれば、いいお母さんになれる」という切ない祈りの裏返しなのではないか。いいお母さんになりたい、そのために具体的に母親ができることは、ひたすら自分だけが痛みや苦しみに耐えて我慢する「自己犠牲」——という、思考の道すじ。
それは、母親たちが孤独であるという事実を、どこか示唆しているのかもしれない。

河崎環 Tamaki Kawasaki
コラムニスト
1973年、京都生まれ神奈川育ち。22歳女子と13歳男子の母。欧州2カ国(スイス、英国)での暮らしを経て帰国後、子育て、政治経済、時事、カルチャーなど多岐に渡る分野での記事・コラム執筆を続ける。2019秋学期は立教大学社会学部にてライティング講座を担当。著書に『女子の生き様は顔に出る』(プレジデント社)。