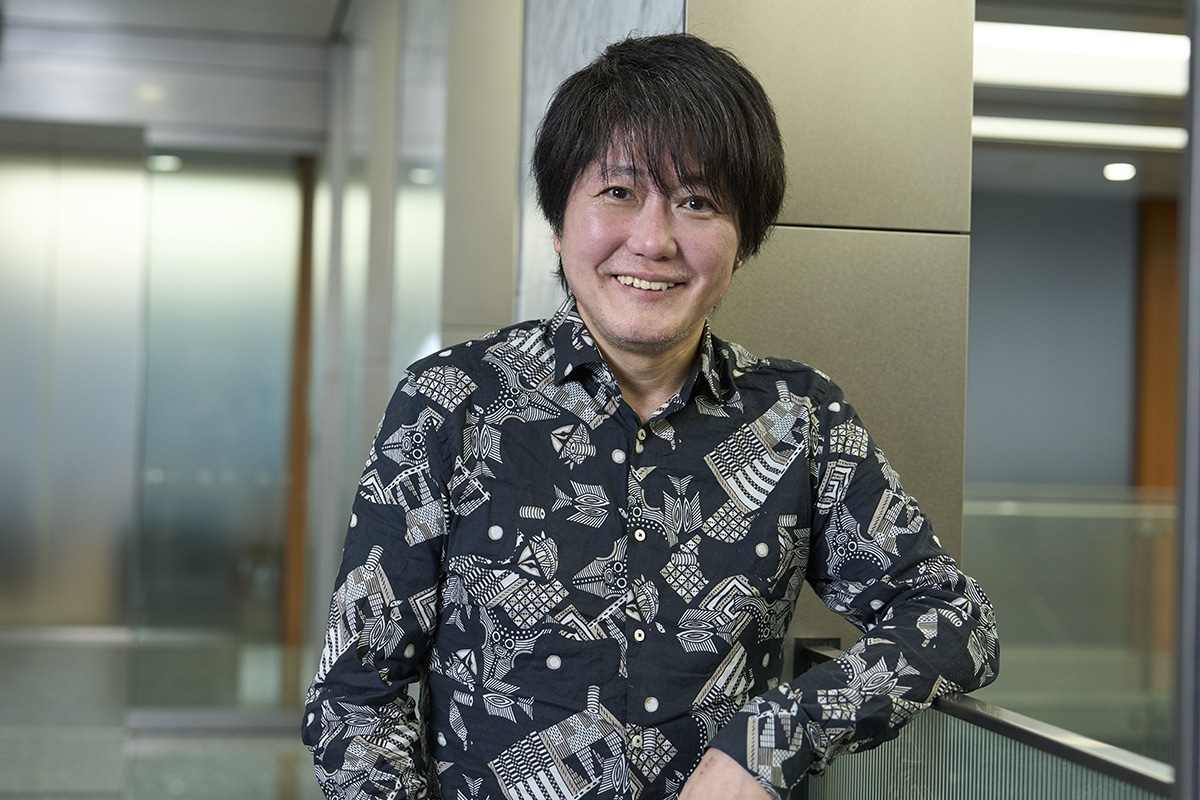「何でも食べられる」のがいい躾(しつけ)、という日本の呪縛
いまや大学3年にもなる娘が幼かった当時、彼女は本当に食べ物の好き嫌いが少なかった。唯一苦手なのは生の玉ねぎくらいで、大人が食べている大抵のものには興味を示すし、大人でさえ躊躇するような珍味にもワクワクと挑戦したがる。「これは絶対に酒飲みになる」と、娘とDNAを分ける私が横で機嫌よく酒瓶にしがみついているのを見て誰もが確信したけれど、いざ成人してみたら、娘は案外にお酒には向いていなかった。
世間では「子供の食べ物の好き嫌い」は大きな子育てトピックの一つ。心身を育てるという観点から、何を口に入れるかが大きな問題なのは、大人の私も同じことだ(私は40の呼び声を聞いたとき、どんな美容法よりもまずお酒の飲み方を見直した)。だが娘の好き嫌いが少ないのは「(いちおう謙遜はしますけれど、まあ最終的には)ワタクシの育て方が良いからですの、ほほほ〜」と信じていた、当時無知で未熟なバカヤロー母だった20年前の私。大勘違いのまま爆進できてしまったのは、ひとえに娘がたまたま大きなアレルギーがなく、わりと大らかさんで忍耐強いので食に警戒心がなく、好奇心旺盛な雑食性向の持ち主だったからに過ぎない。私は未熟な子育てを娘の素質に助けてもらっていたのである。
ところが神様は、そんな勘違い母が9年後にようやく授かった二人目の子供にはバランスよく「最凶のピッキー・イーター」、偏食大魔王の息子を送り込んだ。この息子が、まあ私の人生で見聞きした中でもひどい部類に入るほどの偏食を炸裂させる。アレルギーがあるのかというとそうでもない。ただ、自分が承認した食べ物(ブランド)以外、断固として食べない。例えばおにぎりなら塩むすびに海苔だけ。ベーグルなら特定のお店のプレーン味だけを半分に割ってトーストして、クリームチーズや具など挟まずバターだけでモクモクと食べる。それ以外はブルーベリー味もチーズ味も一切受け付けず、余計なことをしてくれるなと言わんばかりだ。つまり、食の横展開も縦展開も拒否し、たまたまセレンディピティ(魔法的な素敵な巡り合わせ)で受け入れた食べ物だけをピンポイントに好む。
ブロッコリーは食べるけれど、カリフラワーは食べない。ほうれん草は食べるけれど、シンプルなおひたしだけ。リンゴは好きだけれど、皮つきだと手も出さない。ぶどうは緑のみ(のちに巨峰に目覚める)。牛乳は好きだけれど豆乳はありえない、オレンジジュースで許せるのはト●ピカーナだけでしかもパルプ(果実繊維)入りはNO、●〜いお茶以外の日本茶を飲むくらいなら水にするし、パスタはボロネーゼ、ピザはマルゲリータだけをストイックに愛する(バジルは指でつまんでよける)。
「なんなんだ」と私は頭を抱えた。嫌いなものを断固拒否し、食べられるものの方が少ない、日本の幼稚園や学校では協調性なく空気も読めず「生活の基本が全くなっとらん」と大問題とされる子供である。大丈夫なのだろうか(大丈夫じゃないよね)、これでいいのだろうか(よくないよね)、その意志の強さを他のことに振り向けようとは思わないのだろうか(思うわけないよね)?
「どうして同じように育てているのに、上の子と下の子でこんなに違うんだろう」。食の断固たる好き嫌いに現れるように、生活全般がそうだった息子の手強さにとにかくびっくりして悩み育てるうち、娘が13歳、息子が4歳のときに、夫の仕事でスイスへ引っ越すことになった。だけどこんな気難しいヤツ(息子)、スイスなんかに連れていけるんだろうか? あっちで食べられるものなんかあるのかな? 前途は多難、問題山積みでしかなかった。

日本とヨーロッパでは価値観も評価も逆転した
融通の全く利かない自己主張全開の息子と、融通の塊のような調和型の娘。日本の学校では「大問題児」と「手のかからない、素直ないい子」。ところがスイスへ移り住み、国際機関のある街ゆえに本当に世界中から子供達が集まっているインターナショナルスクールに二人を通わせ始めたら、その評価が天地逆転したから、そりゃもうびっくりだ。
自己主張全開の偏食大魔王は、インター幼稚園のアメリカ人おばあちゃん先生に「この子は面白い。確かにまだ感情のコントロールは未熟で激しい性格をしているけれど、頭の回転が早くて知的だし、自分のしたいことをちゃんとわかっている」と、生まれて初めて先生という立場のひとから理解、評価された。インターの環境でも自分の思うところを主張して居場所を獲得し、それゆえに語学力もみるみるうちに獲得し、人気者になって友達をたくさん増やしていった。悪ふざけが過ぎるとそりゃ叱られるけど、彼の食べ物の好き嫌いなんて、誰も問題にしなかった。
だって、人種も文化も宗教も体質もみんな違うから、それぞれの戒律や文化習俗やアレルギーで食べられないもの、食べないものがあって当たり前。宗教上の理由でものすごく厳格なベジタリアンや、ものすごくたくさんアレルギーがあっていつもお母さんお手製のアレルゲンフリーの野菜ケーキと万が一のアナフィラキシーショック用の注射器を持ち歩いている子もいたし、宗教上牛肉がダメとか豚がダメとかも本当に多く、海のない国から来た子は魚を嫌がってスモークサーモンさえ食べなかった。
中には動物愛が深いあまり、あるときを境に「胸が痛む」として一切の肉食を嫌がるようになってしまった9歳の女の子のお母さんが、学校保護者会で悩みを打ち明けた。驚いたことに先生は「食物連鎖の事実や自分がひとりで生きているのではないことに気づいて、世界観が広がったのはとてもいいことね」とそれを認め、「ベジタリアンになるか否かはいずれ本人が自分で選ぶでしょう」と、少女の意思を尊重してしばらく豆食を薦めてみてはと助言したのだ。そんなイロイロな子供達を集めてのお誕生日パーティーなんてのは、もう「それぞれ食べられるものを食べられるだけ食べてね」と言うしかない。
隣の人が何を美味しそうに食べているかには興味を示すけれど、「何を食べていないか」は「へえ、”君は”それは食べないんだね」で軽く流され、理由を根掘り葉掘り聞いたり、まして説教するなんてのは相手の背景を尊重する心に欠け、失礼なのだそうだ。つい罪悪感なんか感じてその理由を「ナスって食感が苦手なんだよね」なんて言い訳したところで、「あ、そうなの。ピザにのせてみると美味しいからやってみたら。だいたいなんでもピザにすると美味しいもんだよ」と、その反応さえも軽い。
食とはその人の人種や国籍や文化や体質や考え方などからくる、「パーソナル(個人的)なもの」だと考えられているのだ。だから教育の名の下に「何を口にするか」を管理監視されない。頭の中の思想も宗教も、説明責任を果たし対話を続ける限り、誰も否定しない。「こうあらねばならぬ」なんてこだわりは、様々な価値観が拮抗する国際社会では「危険」。考え続け、議論し続け、柔軟である限り、魂は自由なのだと知った。
一方「素直で手のかからないいい子」のはずの日本型優等生の娘は、まだ英語に自信がないゆえに口数が少なくおとなしく、誰もが激しく自己主張してナンボのインターでは影が薄くて、先生たちがみんな眉間にしわを寄せて心配していた。「大丈夫かしら」「ひょっとして、精神的に参っているのでは」「いい小児科医がいるので、連れて行ってみます?」
医者!? いえいえ、確かに新しい文化のインパクトに気圧されてはいますが、もともとこの子は控えめで、でも意志はしっかりある子ですし、まして知的にはなんの問題もないどころか賢いですよ?(←親バカ母の主張)
驚いた。インターの環境では、「おとなしすぎる」とはすなわち「知的に、あるいは精神的に何かあるのではないか」と心配されるのだ。娘はどんな課題も全部遅れずに提出し、整理整頓も完璧で、日本だったらそりゃもう優等生扱いだったのだが、彼女のそういうところは「真面目で勤勉」と一行で評価されるのみで、決して成績には大きなプラスにならないのも発見だった。「内容」がエキサイティングだったり意味深いことが重要なのであって、真面目であることは二の次なのだ。
やがて娘は同じようにおとなしめのインドやアジア系の友人ができて笑顔を取り戻し、学校での発言も増えてクラブ活動も楽しめるようになるのだけれど、その頃に担任となったカナダ人の男性教諭が共感を込めてしみじみと語ってくれたのを覚えている。「僕もおとなしいタイプだったから、学生時代は周囲の自己主張の激しい人々の中でサバイバルするのが本当に難しかった。だって”カナダで”おとなしい男子なんですよ、想像できるでしょう?」

「価値観の交差する国際社会では、何を食べるかは結局、哲学の問題よ」
息子の幼稚園のおばあちゃん先生は本当に子育てのいろいろを教えてくれた人で、聞いたらなんとハーバードの大学院を卒業して、夫と一緒に進んでスイスへ移住して来た人なのだった。今から8年前にすでに60歳だった彼女は、きっとその世代ではものすごく先進的な女性だっただろう。「基本的に栄養の問題がなければそれでいいのよ、味覚はいずれ変わるし。こんなに様々な価値観と文化が交わる世界で、クリーン・ザ・ディッシュ・クラブ(出されたものは全て食べよと一方的に強要・奨励する考え方の人々)はナンセンスよね。何を食べるかは結局、哲学の問題よ」、彼女の言葉だ。
その後ロンドン住まいを経て日本への帰国が決まったとき、うちの息子は日本の公立小学校の「給食残しちゃダメ運動」には適応できないだろうなぁ……なんて、母としては真っ暗な気持ちで帰ってきた。でも現代日本ではみんな同じ量の同じメニューを同じマナーで平らげるなんて理不尽なプレッシャーはだいぶ軽くなっていて、日本も案外個人の「多様性」が認められ始めたのかもしれない。
息子はその後、日本の小学校給食らしい「いろいろ食べられるようになりましょう運動」に鍛えられ、いろいろな味との出会いを経験して、心底「美味しい〜大好き〜」とは思えていないにせよ口にできるものはかなり増えたのだから俺の名誉のためにちゃんと書いてくれ、と主張している。

河崎環 Tamaki Kawasaki
コラムニスト
1973年、京都生まれ神奈川育ち。22歳女子と13歳男子の母。欧州2カ国(スイス、英国)での暮らしを経て帰国後、子育て、政治経済、時事、カルチャーなど多岐に渡る分野での記事・コラム執筆を続ける。2019秋学期は立教大学社会学部にてライティング講座を担当。著書に『女子の生き様は顔に出る』(プレジデント社)。