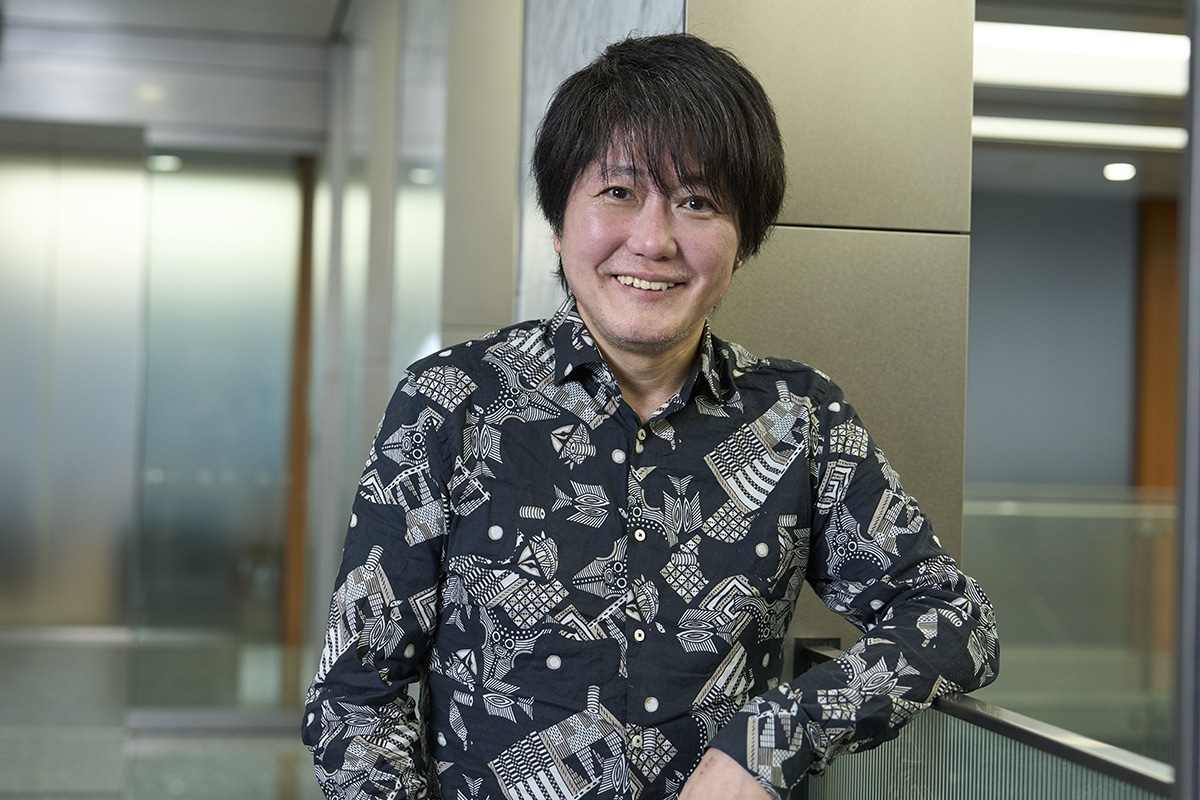「イクメンじゃなくて、父になろう」
というステージへ男たちが上ったのは、この2年くらいのことだ。「ことさらイクメンなんて言ったりちやほやされたりするの、やめようよ。変だよ。男が自分の子供を育てるのなんて、当たり前じゃん?」。
育児するメン、イクメンという言葉は、時代の徒花(あだばな)。そんな言葉がなくなることこそが、イクメン文化の目指す地点だ。イクメン文化が成熟し、そうしてイクメンの終わりが始まった。育児家事に関して、口じゃなくて手や体を実際に動かしている男たちが増えてきた。
言葉はもう、いい。JUST DO IT.
育児や家事は「手を動かしている人が圧倒的にえらい」分野だ。
「家族とは〜」「夫婦とは〜」「人生とは〜」「子育てとは〜」と大上段から立派なことを言ってみたり、家事育児で自分の時間も体力も削っている人の苦労を「理解」したり「共感」したり「前向きに応援」してみたりしたところで、
「で、あなた、何ができるの。具体的に何を助けてくれるの。お腹空かせた子供たちに冷蔵庫の中のものだけで30分以内に食事提供できるの。家族数人が汚したトイレや排水溝掃除のヘドロ触れるの。家族数人分のゴミを家中集めて分別してまとめて捨てに行けるの。山盛りの洗濯物を洗って干して畳んで全部あるべき場所へしまえるの。季節に応じて出現する害虫を大騒ぎせずに退治できるの。子供のウンチオムツ替えられるの。泣き止まない子供をあやせるの。ベビーカーに乗らないと泣きわめく子供を片手で抱っこして、片手で荷物満載のベビーカー押して家へ、あるいは保育園へたどり着けるの?」
との問いにその人がウッと詰まった瞬間、いまこの瞬間に家事育児に従事し手も体も動かし疲れ切っている人たちは、プイと耳を貸さなくなる。他の誰が代わってくれるわけでもない、自分が手を動かしてやらねばならないことが目の前に山積みで、忙しいからだ。
だから「イクメンとは〜」「父とは〜」と、自身の子育て経験も大してない人々の大層なイクメン論を聞くたびに、当のイクメンは「うーん、どうでもいい」と思うらしい。やっぱり、自分が手を動かしてやらねばならないことが目の前に山積みで、忙しいからだ。それが当事者の感想だ。言葉はもう、いいのだ。直接手を貸してほしいのだ。この労働を楽にできる方法を教えてほしい。それができないんならホントすみません、ちょっと黙っててくれます?
日本のイクメンは実践重視へシフトした

イクメン企業アワード2018 理解促進部門賞 表彰式(主催:厚生労働省)にて。左から2番目がCaSy代表取締役 CEO 加茂雄一さん
だから、クラウド家事代行のCaSy(カジー)が「イクメン企業アワード2018」(主催:厚生労働省)にて、今年初めて創設された「理解促進部門賞」を受賞したとのニュースを耳にしたとき、
「日本のイクメンは実践重視へシフトした!」
と膝を打った。
CaSyとは、2014年創業の家事代行ベンチャー企業。「大切なことを、大切にできる時間を創る。」「笑顔の暮らしを、あたりまえにする。」を理念として、それまでの業界平均だった家事代行料1時間4000円を、約半値の2190円にした。それぞれの家庭の「おうちルール」を踏まえて暮らしをサポートするという考え方や、子育てや仕事で忙しい人でもスマホから申し込みができ、各利用者の異なるニーズにきめ細かく応じるサービス設計が人気だ。
そして出色なのは、CaSy独自の「パパへの『ひと手間』アドバイス」。家庭に訪問しない間もキレイを維持できるメンテナンスアドバイスとして、時短になる掃除方法や、ついでの1分でできる簡単なひと手間を、「パパに」伝えるという発想が素敵。パパという人たちは、科学的なメカニズムで伝え、プロの技術でやって見せるととっても素直に吸収

家事代行ベンチャーCaSy(カジー)による、パパへの「ひと手間」アドバイス。「男性の家事に対する当事者意識を醸成」するものとして、高く評価されている。
し、めきめき腕を上げるのだそう。「(妻からだと色々あるけど)プロからなら素直に聞ける、ということなのね……(苦笑)」という感想がつい小声で出てしまうけれど、それが「パパに効く」なら大歓迎じゃない?
「イクメン企業アワード2018」表彰式で、CaSyが「男性の家事に対する当事者意識を醸成する」と言ったのは印象的だった。代表取締役 CEO 加茂雄一さんは、創設されたばかりのイクメン「理解促進部門」で受賞したことについての思いを、こう語っている。
「ママ、パパ、子ども、状況に応じて家事代行とが家事をシェアすれば、家族みんなが不満なく、疲弊せず、笑顔で暮らしていけると思います。私が考えるイクメン=自分たちだけで家事を頑張るだけでなく、家事代行を活用するなど社会とシェアすることが当たり前にできるパパを増やすべく、サービスの提供と啓発活動を続けていきます」
イクメンとは、自分たちだけで家事や育児を頑張るんじゃない、家事育児含めた暮らしを「社会とシェアする」ことを当たり前にできるパパのことだ、との考え方には、新鮮な感動があった。「自分!」とか「家族!」「(ウチの)会社!」というクローズドな単位に固執しない。広く社会とつながるチャンネルを、「組織に所属する」以外にもちゃんと持っているパパ。どうやら、日本のパパたちは居場所をどんどん広げて、経験値を稼いで、かなりイケてる男へと成長を遂げようとしてるように思えるのだけれど、どうだろう?
夫婦役割3.0! なぜ「夫も妻も仕事と家族のケアを担う夫婦スタイル」は実現しなかったのか
『30代の働く地図』(岩波書店/玄田有史・編)という本が10月に刊行され、話題を呼んでいる。東京大学社会科学研究所の玄田有史教授(労働経済学)監修のもと、これからの働きかたを模索する若手研究者たちの11の切り口から、いま頑張っている30代や、それに続く若い世代が自分らしい職業人生を見つけるための気づきのヒントが見つかる本だ。
その第9章「変わりゆく夫婦の約束——家族の生活安定戦略」で、雇用政策・家族政策を専門分野とするリクルートワークス研究所主任研究員・大嶋寧子さんによる戦後の夫婦役割についての考察が、とってもわかりやすくておもしろい。
高度成長期の日本で、大都市圏の企業から続々と生み出される右肩上がりの雇用に地方から労働力が流入。その結果、それまで日本社会の6割は農業を中心とする自営業者と家族従業者だったのが、なんと7割が会社に勤めて妻子を養えるだけの安定的な賃金を得る雇用者となる社会へと大変化した。
大嶋さんはこの高度経済成長が可能にした「男の甲斐性型の働き方」に基づく「夫が稼ぎ、専業主婦の妻が家族のケアを担う」夫婦役割のスタイルを「夫婦役割1.0」と呼び、「企業が推進し、家族が(豊かな生活を約束する最も確実な戦略として)選び取った役割分担」と表現している。そう、あの時代、人は豊かな生活を得るための「戦略」として、そういう夫婦の形を取っていたのだ。正解でもまして最終形でも完成形でもない、そういう暫定的な戦略に過ぎなかったのだ!
やがて石油危機が世界を襲うと、人件費の上昇を抑えたい企業にとって魅力的なパート労働という働きかたが広まった。子供の数が減少して家電製品が浸透すると、妻には働く余裕ができた。一方、進学率の高まりによって教育費が家計を圧迫し、妻には働く理由もできた。財政難に直面した石油危機後の政府が、それまでの社会保障充実の方針をかなぐり捨てて、社会保障の削減に向かったこともあり、家族にとって企業で安定的に働くことはますます重要になっていった。
その結果、夫はますます仕事にまい進する一方で、妻が製造業やサービス業・小売業のパートタイムワーカーとして、あくまで家計補助的な範囲で働くようになった。妻の役割は「家族のケアと仕事」へと変化し、この安定成長期に生まれたのが、夫は更に仕事中心の生活を送り、妻は家族のケアと仕事に向き合う「夫婦役割2.0」だったのだと大嶋さんは論じる。
そして1991年のバブル崩壊。激しい価格競争が中小・零細企業の経営を圧迫し、新卒採用は抑制されて、非正規雇用への依存が高まった。リストラが断行され、かろうじて組織に残れたとしても、賃金上昇は抑制された。妻たちに提供される非正規雇用の数は増え、また若い女性にとっても正社員のポジションを結婚出産きっかけで手放すことへの不安や抵抗感が増大した結果、「働く妻」は急増することとなる。
「男の甲斐性型の働き方」は揺らいだ! にもかかわらず、夫婦双方が平等に仕事と家族ケアを担う共働きスタイルの「夫婦役割3.0」は実現しなかったのだ。その理由を、大嶋さんはこう説明している。
「世帯主の勤め先収入の大幅な減少と配偶者のささやかな収入増の間を埋めたのは、懸命な支出の抑制でした。…(中略)…夫婦は役割負担のバージョンアップではなく、衣食住や娯楽への支出を削りながら生活を守るという、もう一つの『戦略』を選んだのです。…(中略)…その理由として、妻が収入の拡大を目指せる『男の甲斐性型の働き方』をすることが、相変わらず難しかった点が挙げられます。」
企業の経営難は人員削減へと繋がり、現場のサラリーマンたちはより一層の長時間労働と、転勤や単身赴任などに唯々諾々と応じて雇用を死守する傾向へ突入していった。「そのため、家事や育児は変わらず女性に集中していました」。
私たちは「次の世代のためにやる気があるか」?
大嶋さんはこうも言っている。「今度こそ、本格的な夫婦役割の見直しが必要になる」。

長寿化や、AIに代表されるテクノロジーの発展の影響で、企業が「男の甲斐性型」の働き方や家族の人生を支えることは今以上に難しくなっていく。もう疲れちゃったゴメンねー、もう君たちの世代にはムリー、ってなもんである。
そんな時代には「常に将来の転職や独立・起業に備えることが必要になります。そのため、次のキャリアに備えた自己啓発や副業を行ったり、健康を維持しやすく、家族の仕事を制約しにくい働き方を選んだりと言った行動が、長い目で見て自分と家族の生活を安定させます。…(中略)…このような前提に立てば、夫婦それぞれが、収入を得る役割、家族をケアする役割を分担したり、交換したりしながら、そのときどきの役割に適した働き方を選択し続けていく夫婦役割4.0を目指すことが、長い目でより家計を安定させると考えられます」。
CaSy(カジー)がイクメン企業アワード2018・理解促進部門賞を受賞した「イクメン推進シンポジウム2018」では、「男性の育児休業が職場を変える」をテーマにパネルディスカッションも行われた。登壇者の一人、大正大学心理社会学部(社会学)・田中俊之准教授の言葉が印象的だった。
「このように社会的な取り組みは、短期的には成果は出ないもの。北欧でも30年かけて男女平等を実現したように、長期的な目標を立てる必要があります。我々が取り組んでも、我々が生きている間には利益がないかもしれない。次の世代のためにやる気があるか、目先の数合わせに終始するのでなく、我々が受益者にならなくてもやるかどうかが問われているんです」
リクルートワークス研究所主任研究員・大嶋寧子さんも、「夫婦役割3.0」に関してこう語る。
「世間での夫婦の役割分担の頑固さに無力感の漂う意見も見られます。でもその役割分担とは社会のどうしようもない圧力で無理やり選ばされた、というわけではなくて、これまでの家族がそれぞれの時代において、豊かな生活を約束する最も確実な戦略として選び取ったものだったんです。私たちが自分で選んだのにそれをうっかり忘れてしまって、変えようもない運命だと思うのはやめようよ、というのが私の研究のメッセージです」
時代に応じた暫定的な戦略は、新しい時代には新しい社会に応じてまた別のものになる。時代はすっかり様変わりした。私たちは、男も女も今度こそ、自分たちを更新して、バージョンアップできるだろうか。

河崎環 Tamaki Kawasaki
コラムニスト
1973年、京都生まれ神奈川育ち。22歳女子と13歳男子の母。欧州2カ国(スイス、英国)での暮らしを経て帰国後、子育て、政治経済、時事、カルチャーなど多岐に渡る分野での記事・コラム執筆を続ける。2019秋学期は立教大学社会学部にてライティング講座を担当。著書に『女子の生き様は顔に出る』(プレジデント社)。